iDeCoに年末調整、確定申告は必要?必要な理由、手続きの流れなど解説
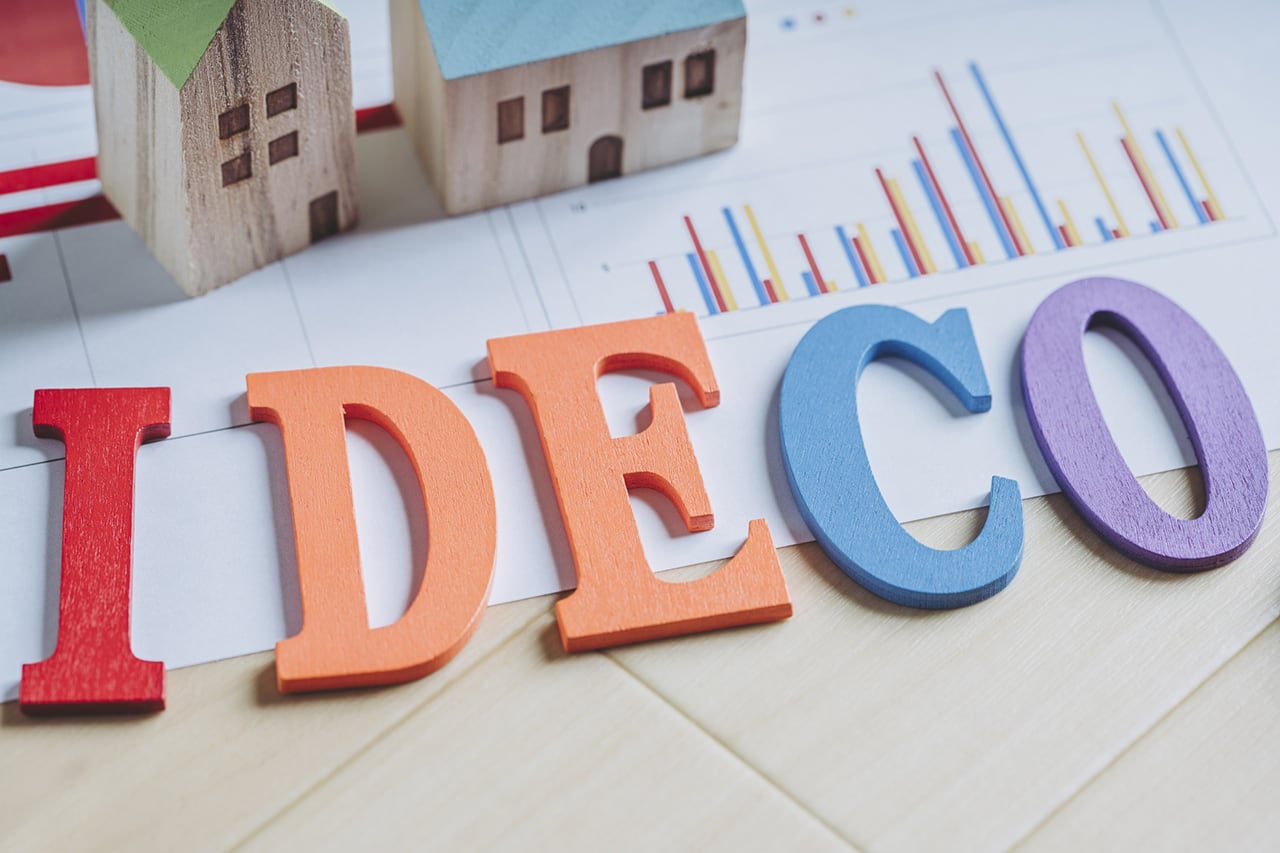
iDeCoは節税メリットが大きいと聞いたことはありませんか。しかし、このメリットを活かすには年末調整や確定申告で必要事項を記入して提出する必要あります。この記事では、iDeCoを有効活用するのに年末調整や確定申告が必要な理由や、手続きに必要な書類や手順、記入の仕方などを解説しています。iDeCoを賢く活用するための参考にしてください。
iDeCoに加入者は、年末調整、確定申告が必要?
iDeCoで節税するには年末調整か確定申告が必要です。必要な手続きは以下の通りで、
会社員または自営業なのかで必要な手続きや手順が異なります。
| 会社員・公務員の方 | 自営業の方 |
|---|---|
| 年末調整 ※期限を過ぎると自身で確定申告を行う必要があります |
確定申告 |
iDeCoで年末調整や確定申告をする目的は、所得税や住民税の節税の恩恵を受けるためです。iDeCoの毎月の掛け金は、すべて課税所得から差し引くことができます。また、定期預金、保険、投資信託などを運用して得た利益についても同じく非課税になります。
万が一、確定申告を忘れてしまったとしても、その年の翌年1月1日から5年間の間に還付申告の手続きをすれば、還付金を受け取ることができます。
iDeCoで年末調整をすると所得控除が受けられる
iDeCoで積み立てた掛け金は「小規模企業共済等掛け金控除」の対象のため、所得控除の対象になります。
所得税は「課税対象=所得対象-所得控除」の計算式で計算し、「課税所得」に所定の税率をかけて算出します。この所得控除の一つとしてiDeCoの掛け金を差し引けます。医療費控除や生命保険料控除を受けている人は、これに類したものと考えればよいでしょう。
(参考)所得税控除とは
所得税とは、所得の合計額から控除対象の合計額を差し引くことで、税負担を軽くする制度です。
iDeCoの節税額の計算方法について
・所得税に関する計算方法
iDeCoによる所得税の節税額の計算方法は、
「年間の掛け金×(課税所得金額に応じた)税率」
です。つまり、下記表のとおり掛け金が増えるほど節税効果も大きくなります。
・住民税に関する計算方法
住民税も所得税と同じように「年間の掛け金×(課税所得金額に応じた)税率」分を節税できます。
住民税は「均等割額(納税者が一律で負担する税金)+所得割額(所得に応じて決まる税金)」で決まります。このうち、所得割額の計算の元となる所得額から掛け金を差し引けるため、上記のような節税が可能です。
所得割の標準税率は居住地の都道府県、市区町村によって違うことがあるため、各自治体のHPなどで確認してください。
節税効果のシュミレーション例
下記の表を参照ください。
仮にIDeCoの掛け金が月2万円で年間24万円を納めていたとします。
このケースでは、所得税率が10%、住民税が10%なら節税額は、
24万×10%+24万×10%=4万8000円です。
つまり、下記表の通り同じ掛け金でも課税所得や年間掛金が多い人ほどiDeCoの節税効果が大きくなります。
|
課税所得 |
所得税税率 |
住民税税率 |
年間掛金 |
税制優遇額 |
|---|---|---|---|---|
|
195万円以下 |
5% |
10% |
24万 |
3万6千円 |
|
195万~330万円以下 |
10% |
4万8千円 |
||
|
330万~695万円以下 |
20% |
7万2千円 |
||
|
695万~900万円以下 |
23% |
7万9千2百円 |
||
|
900万~1800万円以下 |
33% |
10万3千2百円 |
||
|
1800万~4000万円以下 |
40% |
12万円 |
||
|
4000万円~ |
45% |
13万2千円 |
ただし、iDeCoはあくまでも老後資金形成を目的にした制度です。運用状況によって、元本割れのリスクもあるので補足的なメリットと考えて、無理のない範囲で掛け金を設定しましょう。
iDeCo、年末調整(もしくは確定申告)に必要な準備と手順
iDeCo活用に年末調整または確定申告は欠かせません。ここでは、それぞれに必要な書類、書き方や手順を解説します。
【年末調整の準備と手順】
会社員・公務員が年末調整を行う場合に必要となる書類は以下となります。
必要な書類一覧
|
書類 |
受取先 |
|
|---|---|---|
|
1 |
小規模企業共済等掛け金払込証明書 |
国民年金基金連合会 |
|
2 |
給与所得者の保険料控除申告書 |
勤務先 |
<手順>
会社員・公務員が年末調整を行う場合の手順は以下となります。
1.「小規模企業共済等掛け金払込証明書」届いたら保管しておく
2.「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先から受け取り、必要事項を記入
3.1、2を勤務先に提出(払込証明書を添付する)
1.証明書は国民年金基金連合会からはがきで送られていきます。通常10月頃に届きますが、初回の掛け金の支払い月によって変わる場合もあります。また、紛失した場合は再発行できますが、再送までに期間がかかるので大切に保管しておきましょう。
2. <記入方法>「確定拠出型年金法に規定する個人型年金加入者掛け金」と「合計(控除額)」の欄に掛け金合計を記入
3.ただし、iDeCoの掛け金を給与から差し引いている「事業主払込」場合は、年末調整の手続きはありません。また、年末調整が何らかの理由でできない場合は確定申告が必要になります。確定申告の流れは次項で説明します。
確定申告の対象者|年末調整未実施の会社員と公務員の場合
勤務先での年末調整が間に合わなければ確定申告が必要になります。 記入用紙が2種類あるので注意してください。
【確定申告の準備と手順】
確定申告に必要な書類と手順は以下になります。
必要な書類一覧
|
書類 |
受取先 |
|
|---|---|---|
|
1 |
小規模企業共済等掛け金払込証明書 |
国民年金基金連合会 |
|
2 |
確定申告書A |
税務署、役所、国税庁HP ※e-Tax(電子申告)でも可 |
<手順>
会社員・公務員が確定申告を行う場合の手順は以下となります。
1.「小規模企業共済等掛け金払込証明書」届いたら保管しておく
2.確定申告書を入手する
3.確定申告書A、「小規模企業共済等掛け金払込証明書」を添付し、郵送などで提出(またはe-Taxで提出)
1.証明書は国民年金基金連合会からはがきで送られていきます。通常10月頃に届きますが、初回の掛け金の支払い月によって変わる場合もあります。また、紛失した場合は再発行できますが、再送までに期間がかかるので大切に保管しておきましょう。
2.税務署や役所で用紙を入手するか、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」からダウンロードして印刷。ほかにe-Tax(電子申告)で申請する方法もあります。
・記入用紙 確定申告書A
<記入方法>
・第1表の「小規模企業共済等掛け金控除⑦」の欄に「小規模企業共済等掛け金払込証明書」に記載された掛け金総額を書き込む。
・第2表「小規模企業共済等掛け金控除⑦」の「掛け金の種類」の欄に「個人型確定拠出年金」と記入
・第2表の「支払掛金」、「合計」欄に、「小規模企業共済等掛け金払込証明書」に記載された掛け金総額を記入
3.詳細は国税庁HPで確認できます。
確定申告の対象者|自営業(個人事業主やフリーランスを含む)、無職の人
【確定申告の準備と手順】
確定申告に必要な書類と手順は以下になります。
必要な種類一覧
|
書類 |
受取先 |
|
|---|---|---|
|
1 |
小規模企業共済等掛け金払込証明書 |
国民年金基金連合会 |
|
2 |
確定申告書B |
税務署、役所、国税庁HP ※e-Tax(電子申告)でも可 |
<手順>
自営業(個人事業主やフリーランスを含む)、無職の場合、確定申告を行う場合の手順は以下となります。
1.「小規模企業共済等掛け金払込証明書」届いたら保管しておく
2.確定申告書を入手する
3.確定申告書B、「小規模企業共済等掛け金払込証明書」を郵送などで提出(またはe-Taxで提出)
1.証明書は国民年金基金連合会からはがきで送られていきます。紛失した場合は再発行できますが、再送までに期間がかかるので大切に保管しておきましょう。はがきが届く時期は10月頃ですが、初回の掛け金の支払い月によって変わる場合もあります。
2.税務署や役所で用紙を入手するか、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」からダウンロードして印刷。ほかにe-Tax(電子申告)する方法もあります。
・記入用紙 確定申告書B
<記入方法>
・第1表の「小規模企業共済等掛け金控除⑬」の欄に「小規模企業共済等掛け金払込証明書」に記載された掛け金総額を書き込む。
・第2表「小規模企業共済等掛け金払込証明書」の「掛け金の種類」の欄に「個人型確定拠出年金」と記入
・第2表の「支払掛金」、「合計」欄に、「小規模企業共済等掛け金払込証明書」に記載された掛け金総額を記入
3.詳細は国税庁HPで確認できます。
iDeCo、年末調整(もしくは確定申告)に関するよくある質問
ここでは、年末調整または確定申告でiDeCoの節税をするよくある質問をまとめました。
<質問>年末調整(もしくは確定申告)をしないと節税の効果はないの?
<アンサー>
繰り返しになりますが、節税メリットを得るには年末調整もしくは確定申告が必要です。失念しないよう注意してください。また、年末調整を行えなかった会社員、公務員の人は、確定申告すれば節税できるため、あきらめないで申告しましょう。
<質問>年末調整の申告期限や提出方法は企業によって異なるのでしょうか?
A.
年末調整の申告期限や提出方法は企業によって異なります。一般的な提出期限は11月中~下旬ですが、勤務先に合わせて準備をしておきましょう。
また、勤務先によっては「給与所得者の保険料控除申告書」の配布・記入を行わず、専用の人事システムに入力する場合もあります。
<質問>「小規模企業共済等掛け金払込証明書」の紛失してしまったら?
A.
「小規模企業共済等掛け金払込証明書」はハガキ(手紙)で送られてきます。通常、表面に「小規模企業共済等掛け金払込証明書」と赤字で強調されているので、見落としや紛失、破棄がないように注意しましょう。もし失くしてしまったら、時間はかかりますが再発行できます。iDeCoの口座がある金融機関に早めに問い合わせておきましょう。
<質問>所得控除や還付のメリットは本人だけに適用されるのでしょうか?
A.
iDeCoの所得控除や還付のメリットは本人だけに適用されます。例えば、専業主婦(夫)が配偶者に代わって掛け金を払っても、所得控除は受けられません。
まとめ
iDeCoで節税メリットを得るためには、年末調整か確定申告が必要です。所得税や住民税の節税効果につながり、還付金を受け取れる可能性があるので忘れずに手続きをしておきましょう。
IOSマネーセミナーでは無料のマネーオンラインセミナーを開催しております。老後資金や年金はもちろん、iDeCoやNISAなど資産運用の基礎についてスキマ時間に、将来に活かせて得するコツを学べます。
今ならFP無料相談ができる参加特典付きです。ぜひ気軽にご参加ください。




