確定拠出年金のデメリットとは|個人型・企業型それぞれの違いもふまえわかりやすく解説
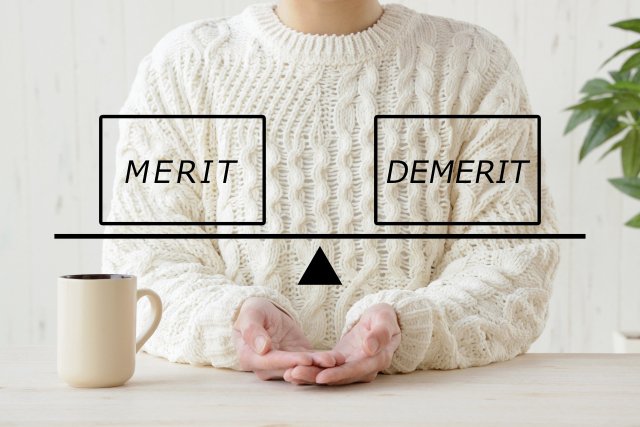
確定拠出年金は、個人型(iDeCo)と企業型(企業型DC)の2種類があります。この記事では、資産運用を検討している人に向けて、2種類の確定拠出年金のデメリットに着目して解説します。
また、それぞれのメリットや加入条件などの違い、2022年4月からの改正ポイントも紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
確定拠出年金は2種類ある
確定拠出年金とは、毎月掛金を積み立てて60歳を過ぎてから年金として受け取ることができる年金制度です。確定拠出年金には、個人向けの年金制度の個人型確定拠出年金があります。一般的に、iDeCo(イデコ)と呼ばれています。
また、企業向けの年金制度は企業型確定拠出年金です。通称で企業型DCとも呼ばれています。個人型確定拠出年金の加入制限はありませんが、企業型(企業DC)は社内で年金制度を設けている企業のみが対象です。
確定拠出年金|種類ごとのメリット・デメリット
確定拠出年金に加入する際、個人型(iDeCo)と企業型(企業DC)のメリットを理解するだけでなく、デメリットもあわせて把握しておくことが重要です。
個人型(iDeCo)のメリット・デメリット
メリット
個人型(iDeCo)に加入するメリットは、3つの税制優遇措置を受けられることです。毎月の掛金の全額に所得控除を受けることができ、運用益はすべて非課税になります。また、年金や一時金を受け取る際は、所得控除や公的年金等控除、退職所得控除などの税負担を軽減できることもメリットの一つです。
さらに、元本確保商品と投資信託の運用商品もあるため、元本割れのリスクを避けたい人は元本確保商品の定期預金や保険などを選ぶとよいでしょう。離職や転職の際は積立金を持ち運べるため、企業型(企業DC)から個人型(iDeCo)へ年金資産を移せます。
デメリット
手数料がかかる
個人型(iDeCo)に加入するデメリットは、さまざまな手数料を支払わなければならないことです。たとえば、加入時に口座を開設する場合や移換する場合に手数料がかかります。また、口座を管理してもらうための口座管理手数料も必要です。他にも、次のような手数料を支払う必要があります。
・信託報酬
・給付事務手数料
・還付事務手数料
手数料は加入者が支払う必要があるため、多くの手数料を支払うことで元本割れになってしまうかもしれません。
加入者によっては、メリットがメリットにならないことがある
個人型(iDeCo)には上述したようなメリットがあるものの、加入者によってメリットを得られないケースもあります。たとえば、掛金の全額は所得控除を受けられますが、専業主婦(主夫)が個人型(iDeCo)に加入しても所得がないため、メリットにはなりません。
また、公務員などの年金や退職金の金額が多い職業の場合、退職時に公的年金などで控除の上限額に達してしまう可能性があります。個人型(iDeCo)で年金や一時金を受け取っても、控除を受けられないかもしれません。
企業型(企業型DC)のメリット・デメリット
メリット
企業型(企業DC)のメリットは、投資のプロが運用商品を選定しているため、資産運用が初めての人でも運用商品が選びやすいことです。また、コストが低い金額に設定されているほか、メリットの1つです。
デメリット
購入したい運用商品がない場合がある
企業型(企業DC)は運用商品を選べますが、運営管理機関を選ぶことができません。運用商品の選定は企業が選ぶのが一般的なため、購入したい商品がない、自分の意思で運用商品を選べない点がデメリットです。
扶養している配偶者や家族は加入できない
企業型(企業DC)の加入対象者は、厚生年金の被保険者のみです。企業型(企業DC)は企業の従業員のみを対象にしている制度のため、専業主婦(主夫)など、被保険者が扶養している配偶者や家族は対象外になります。
個人型・企業型共通のメリット・デメリット
メリット
個人型(iDeCo)・企業型(企業DC)に共通するメリットは、それぞれに3つの税制優遇措置が設けられていることです。掛金の全額が所得控除を受けられる、運用益は非課税になる、年金や一時金の受取時も税控除を受けることができます。
また、離職や転職によって、企業型(企業DC)から個人型(iDeCo)へ、個人型(iDeCo)から企業型(企業DC)へ積立金を持ち運ぶことも可能です。
デメリット
確定拠出年金のデメリットは自分で運用しなければならないため、将来の年金額が確定されないことです。また、資産運用は大きなリスクを伴う場合があります。確定拠出年金に加入する前に運用に関する情報収集をし、知識を深めておく必要があるでしょう。
確定拠出年金は原則として、60歳になるまでは掛金を引き出せないため、緊急で資金が必要になった場合は対応できません。さらに、掛金には上限や下限が設定されているため、設定金額の範囲内で運用する必要があります。
加入条件は、基本的にどちらも60歳未満までになっていますが、企業型(企業DC)は条件付きで65歳まで加入可能です。2022年の加入年齢に関する法改正の詳細は、最後の項目で解説します。
確定拠出年金|個人型と企業型の主な違い
個人型と企業型は、どちらも老後の生活資金を目的にした制度ですが、それぞれ違いがあります。個人型(iDeCo)は基本的に自助努力のための制度で、自分の老後に必要な資金は自ら備えることを目的にしています。
一方で、企業型(企業DC)は企業ごとに設けている退職金制度や福利厚生の一環です。
個人型(iDeCo)と企業型(企業DC)の違いについては以下で詳しく解説しているため、参考にしてください。
【個人型と企業型の主な違い】
個人型と企業型の違いを以下の表にまとめました。加入する際に役立ててください。
|
個人型(iDeCo) |
企業型(企業型DC) |
|
|---|---|---|
|
加入対象者 |
・加入は任意 ・誰でも加入できる ・加入対象者:会社員・公務員など(国民年金第2号被保険者で60歳未満の人)、自営業・その家族、学生など(20歳~60歳未満の国民年金第1号被保険者かつ国民年金の保険料の納付者)、専業主婦(主夫)・パートタイム労働者など(20歳~60歳未満の国民年金第3号被保険者) |
・会社が退職金制度で導入している場合は加入できる ・加入対象者:従業員・役員(60歳未満の厚生年金被保険者) ・加入するかどうかは本人の意思で選べる場合と、加入対象者が年金規約によって定められた人のみの場合がある |
|
掛金負担者 |
・加入者自身が負担する(中小事業主掛金納付制度を導入している企業の場合、事業主が掛金を負担することも可能) |
・会社が負担するのが一般的 ※マッチング拠出による掛金の上乗せも可能(年金規約の定めにより、従業員は掛金を上乗せできる仕組み) |
|
納付方法 |
・個人名義の口座からの振替が可能(会社に相談すれば、給与天引きによる納付もできる) |
・原則として会社が納付する |
|
口座管理手数料 |
・手数料のすべては自己負担 |
・手数料の種類によって異なる ・口座管理手数料は会社負担になるケースもあるものの、規約に定めていれば従業員が自己負担するケースもある |
|
給付方法 |
・原則として60歳以降 ・一時金もしくは年金のどちらかを選べる |
・原則として60歳以降 ・一時金もしくは年金のどちらかを選択する、併用することも可能 ・会社の年金規約に定められている場合、受け取り方を選べないケースもある |
|
運用商品、運用方法 |
・契約する金融機関のラインナップから自分で選び、運用できる |
・会社が選定したラインナップの中から選び、自分で運用する |
|
申込み手続き |
・加入者自身が加入したい金融機関を選定し、加入の申込み手続きを行う |
・会社が選定した金融機関に加入の申込み手続きを行う |
2022年4月からの確定拠出年金制度の改正にも注意
法改正による個人型(iDeCo)の加入要件の緩和されることで、加入可能年齢の上限が上がり、年金の受給開始年齢の上限も同時に引き上げられます。法改正が行われる背景は、高齢の労働者の割合が増加傾向にあるためです。確定拠出年金のデメリットとして挙げられる加入可能年齢の制限については、以下で解説します。
(2022年5月~)個人型・企業型と共に加入可能年齢が拡大
個人型(iDeCo)の加入可能年齢は原則として60歳未満までとされていますが、法改正後は会社員・公務員などの第2号被保険者なら65歳まで加入できるようになります。
また、扶養する家族は基本的に従来通り60歳未満までとなっていますが、国民年金の加入者なら65歳まで加入できます。
一方で、企業型(企業DC)は原則として60歳未満までで、同一事務所で雇用されている場合は延長しても65歳未満までです。法改正後は、厚生年金被保険者なら70歳未満までの加入が可能です。また、加入条件も緩和されるため、別の会社に転職した場合でも加入し続けることができます。
まとめ
確定拠出年金に加入した場合、手数料がかかる、加入年齢が制限されているなどのデメリットもありますが、法改正後は加入年齢制限や加入条件が緩和されます。
ただし、資産運用の知識がなければ元本割れなどのリスクを負いかねません。
IOSの無料マネーセミナーを開催しております。老後資金や年金はもちろん、iDeCoやNISAなど資産運用の基礎についてスキマ時間で将来に活かせて得するコツを学べます。
今ならFP無料相談ができる参加特典付きです。ぜひ気軽にご参加ください。




