確定拠出年金はいくらもらえる?掛金の平均額や運用のコツ、老後資金の積立方法を解説
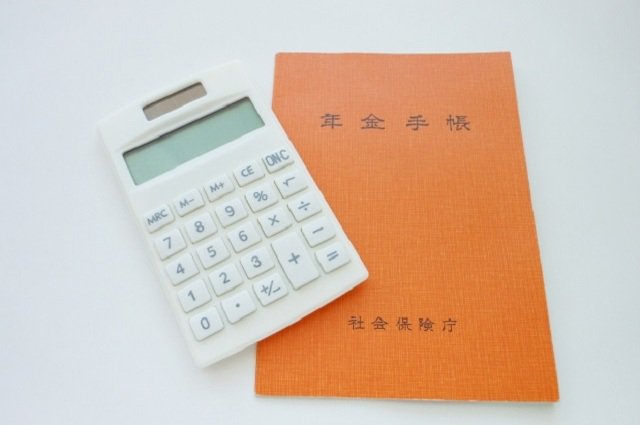
確定拠出年金とは、掛金を加入者が捻出し運用する、私的年金の一つです。確定拠出年金で、将来どのくらいのお金がもらえるのかは、掛金や運用結果に応じて異なります。この記事では、マネー初心者に向けて、確定拠出年金とは何なのか、掛金の平均額や運用のコツなどを詳しく解説します。ぜひ、参考にしてください。
確定拠出年金とは
確定拠出年金とは、私的年金の1種です。加入は任意で、加入者自身が掛金を積み立てる形になります。積み立てた掛金を用いて運用をしていき、運用結果によって将来受け取れる金額が変動するタイプの私的年金です。そのため、資産が増える場合もありますが元本割れするケースもあります。
確定拠出年金は、「個人型」と「企業型」の2種類に分かれており、それぞれに特徴が異なります。以下では、個人型確定拠出年金と企業型確定拠出年金について、詳しく解説します。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金は、個人で掛金を捻出して資産運用する私的年金です。「iDeCo」という愛称で知られていますが、「individual-type Defined Contribution pension plan」を略した言葉です。加入対象者は、自営業者や専業主婦(夫)、公務員やフリーランス、企業型に加入していない会社員などで、掛金はすべて自分で拠出します。
企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金とは、企業が従業員の老後の年金などを準備するための制度です。対象者は、企業型年金制度を設けている企業の会社員です。勤め先で企業型年金制度を実施していない場合には、加入できません。企業型確定拠出年金の掛金は企業が拠出します。ただし、条件を満たしていれば、加入者自らが一定金額を拠出することも可能です。
確定拠出年金のメリット・デメリット
確定拠出年金には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。以下では、確定拠出年金のメリット・デメリットを詳しく解説します。
メリット
確定拠出年金に加入することで、節税効果が期待できます。確定拠出年金の掛金は所得控除の対象となるため、所得税や住民税の負担が軽くなります。また、確定拠出年金で得た収益も非課税です。一般的に、株やFXなどで資産運用した場合、利益分は課税対象ですが、確定拠出年金は非課税のためお得に運用できます。
デメリット
確定拠出年金は、運用結果によって将来受け取れる金額が変わるタイプの私的年金です。つまり、運用が上手くいけば利益が出ますが、運用が上手くいかなかった場合には損をします。運用次第では、元本割れするリスクもあるため注意が必要です。また、原則60歳までお金の引き出しができないため、急にまとまったお金が必要になっても引き出せません。
確定拠出年金はいくらもらえる?
前述したように、確定拠出年金は運用結果次第で受け取れる金額が異なります。受給額のシミュレーションは2つの算出方法があるため、以下では各算出方法について詳しく解説します。
積立額から将来いくらになるのかを求める
「年利3%で毎年20万円積み立てた場合に、20年後どの程度の年金がもらえるか」といった、最終的な資産額を算出したい場合は、年金終値係数を用いましょう。
年金終値係数とは、現在の積立金額を複利運用した際に将来いくらになるのか、と示した係数です。年利や期間を基にして終値係数が定められた「年金終値係数表」から、自分の終値係数を確認しましょう。最終的に受け取れる年金額は、「毎年の積立額×年金終値係数」という計算式で算出します。
受け取りたい金額から元手を求める
「20年後に年間150万円ずつ年金を受け取りたいとき、年利3%で複利運用する場合には元手がいくら必要か」といった元手の資金を求める際には、年金現価係数を用いましょう。
年金現価係数とは、将来受け取りたい金額をもらうためには、元手としてどの程度の資金が必要か、を示した係数です。年金終値係数同様に、年利や期間と基にして定められた「年金現価係数表」から、自分の現価係数を確認しましょう。元手がどのぐらい必要かは、「受け取りたい金額×年金現価係数」で求められます。
掛金の平均額
掛金の平均額は、個人型か企業型かによって異なります。以下では、それぞれの掛金の平均額を解説します。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の場合
個人型確定拠出年金は、加入者本人が掛金を決定できます。掛金は、月額5,000円~拠出限度額の範囲内であれば、自分で自由に決められます。拠出限度額は、国民年金の加入資格区分によって異なるため、確認してみましょう。iDeCo公式サイトによる、掛金平均は以下のとおりです。
(2021年10月時点)
|
対象 |
掛金平均 |
|---|---|
|
全体平均 |
15,942円 |
|
第1号 自営業者やフリーランス |
28,368円 |
|
第2号 会社員や公務員 |
14,316円 |
|
第3号 専業主婦(夫) |
15,214円 |
第1号は拠出限度額が月額68,000円ともっとも多くなっているため、平均掛金が他の資格区分と比べると高めになっています。
第2号の場合には、勤めている企業に企業年金がない、企業型確定拠出年金に加入しているなど、条件によって拠出限度額が異なるため確認しましょう。
※参考:iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入等の概況|iDeCo公式サイト
企業型確定拠出年金の場合
企業型確定拠出年金の場合、事業主掛金は会社が決定するため、基本的に自分で掛金を決めることはできません。しかし、加入者によって上乗せ拠出できるマッチング拠出という制度を取り入れている企業もあり、その場合には自分で掛金を決めて上乗せできます。
ただし、掛金はいくらでも拠出できるわけではありません。「加入者掛金累計が事業主掛金累計と超えない範囲であること」、「事業主掛金累計と加入者掛金累計の合計が掛金拠出限度額累計を超えないこと」の2つを満たした範囲内で金額が決められます。
企業年金連合会によると、2019年度決算のマッチング拠出利用率は30.2%、平均月額は8,526円となっています。加入者掛金の平均額は以下の表のとおりです。
|
加入者掛金 |
拠出状況 |
|---|---|
|
5,000円未満 |
39.5% |
|
5,000~10,000円未満 |
58.1% |
|
10,000~13,750円以下 |
2.4% |
このように、5,000~10,000円未満の割合がもっとも高くなっています。しかし、5,000円未満の割合も約4割と多く、ほとんどが10,000円未満だということがわかります。
※参考:2019(令和元)年度決算 確定拠出年金実態調査結果(概要)|企業年金連合会
確定拠出年金を運用するコツ
確定拠出年金を運用する際には、ポイントを押さえることが重要です。ここでは、運用のコツを解説します。
目標に合わせたプランを立てる
まずは、目標を明確にして、どの程度リスクを取る必要があるのかを検討してプランを立てます。また、年代によって残りの運用期間やライフステージが異なります。そのため、年代に合わせた商品を選びましょう。たとえば、残りの運用期間が長い20~30代は多少リスクのある運用でも構いません。40~50代は残り運用期間が短いため、安定性を重視しましょう。
年に1回は見直す
資産運用は年に1回程度は見直しを行います。定期的に運用商品の資産残高や目標を達成しているのかを確認しましょう。資産配分割合がずれている場合には、運用を見直すリバランスが重要です。リバランスとは、初めに設定した資産配分に調整し直すことです。リバランスにより、運用目的やリスクなどのずれを見直せます。
確定拠出年金以外の老後資金の積立方法
老後資金を積み立てる方法は、確定拠出年金以外にもあります。以下では、その他の老後資金積立方法について解説します。
年間40万円が非課税になるつみたてNISA
つみたてNISAとは、長期の積立・分散投資を支援するための制度で、税制優遇が受けられます。月額100円から、最大33,000円までの少額投資が可能です。つみたてNISAは年間40万円までの投資なら非課税となるため、節税しながら資産運用できます。ただし、投資額が年間40万円と少額で、大きな金額を投資したい場合には不向きです。
つみたてNISAについて知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
※参考:NISAの始め方 一般NISA・つみたてNISA・iDeCoの特徴も合わせて解説
定期預金とは、普通預金よりも金利が高い預金です。最短1か月から最長10年の範囲で預金でき、設定期間中は引き出しができません。元本割れのリスクがなく手数料もかからないため、ローリスクで運用できます。ただし、普通預金より金利は高めですが運用効率は高くない、銀行が破綻した場合は銀行窓口1つにつき1,000万円までしか補償されません。
会社員向けの財形貯蓄
会社員向けの財形貯蓄とは、勤務先で天引きして積み立てる形の貯蓄制度です。目的別に一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の3種類に分けられます。天引きされた給料は企業が提携している金融機関に払い込まれて運用されるため、自分で何か手続きをする必要がありません。ただし、企業で財形貯蓄制度を導入していない場合には利用できないため、注意しましょう。
自営業・フリーランス向けの小規模企業共済
小規模企業共済は、企業に勤めていない自営業者やフリーランス向けの制度です。毎月1,000~70,000円までの範囲内で掛金を拠出できます。掛金が所得控除の対象となるため、節税効果が得られるというメリットがあります。ただし、掛金納付月数が24か月を下回る場合には、元本割れしてしまうため、納付月には注意しましょう。
確定拠出年金についてよくある質問
ここでは、確定拠出年金についてよくある質問を4つ紹介します。ぜひ、参考にしてください。
誰でも加入できますか?
原則として、20~60歳までの人が加入できます。ただし、条件によっては加入できない人もいます。加入が認められない人の条件は、以下のとおりです。
・第1号被保険者の内、国民年金保険料を納めていない(免除も含む)
・企業型拠出年金の対象者で、個人型確定拠出年金に入ることが勤務先で認められていない
いくらから始められますか?
月額5,000円から、1,000円単位で掛金を決められます。前述したように、加入している年金の区分や職業などによって拠出限度額は異なるため、自分が加入している区分などを確認しましょう。
途中で解約できますか?
確定拠出年金は途中解約ができず、原則として60歳まで引き出せません。ただし、東日本大震災の被災者など、特殊な事情に該当する場合は引き出し可能です。該当しない場合、掛金を積立せずに運用することはできます。
転職時・中途退職時に必要な手続きなどはありますか?
転職する場合、転職先に企業型確定拠出年金制度があるかどうか調べましょう。ある場合には、転職先の担当部署に連絡し、手続き方法を確認します。企業型確定拠出年金制度がない場合、個人型確定拠出年金へと移換できます。自営業や専業主婦(夫)になる場合も同様に、個人型確定拠出年金へ移換可能です。
まとめ
確定拠出年金とは私的年金の一つで、個人型と企業型の2種類に分けられます。掛金が所得控除の対象となるため、節税しながら資産運用が可能です。老後資金の積立方法は他にもあるため、自分に合ったものを選びましょう。
IOSの無料マネーセミナーを開催しております。老後資金や年金はもちろん、iDeCoやNISAなど資産運用の基礎についてスキマ時間で将来に活かせて得する知識が学べます。
今ならFP無料相談ができる参加特典付きです。ぜひ気軽にご参加ください。





